ソフトウェア開発費の見積り、プロジェクトマネジメント、
発注者と受注者の間の合意形成等に参考となる情報を不定期に掲載していきます。
生成AIが拓くデジタル経営
第1回 2025年の生成AI動向と企業導入の現在地


株式会社VIVINKO 代表取締役 井上 研一
2025年現在、生成AIは単なる研究領域の技術ではなく、企業のIT戦略や業務変革の中核をめぐる競争軸の一つとなっています。2023年にChatGPTが登場して以来、わずか2年あまりというスピードで、多くの企業が導入フェーズを迎えています。
一般社団法人日本情報システムユーザー協会(JUAS)が実施した「企業IT動向調査2025」によれば、言語系生成AIを導入済み/導入準備中と回答した東証上場企業とそれに準ずる企業の割合は、41.2%に達しました。前回調査では26.9%であり、1年で14.3ポイントの伸長です。
慢性的な人手不足や、レガシーシステムの運用負荷といった課題が深刻化し「2025年の壁」と言われます。生成AIは単なる「業務効率化の道具」を超えて、企業の業務プロセスや組織モデルを再設計する「変革の原動力」として位置づけが変わりつつあります。
■主要3社の最新モデル
2025年8月に発表されたOpenAIのGPT-5は、大きな注目を集めました。軽量モデルと高性能な推論モデルを、ルーター機能によって文脈に応じて自動で切り替える設計を採用しています。一部の利用者からは「GPT-4oの方が応答速度や使い勝手で勝っていた」という声も聞かれ、期待の高さゆえに評価が厳しくなる様子もうかがえます。OpenAIは、GPT-5でハルシネーション(誤情報生成)を従来比80%削減できたと主張しています。
GoogleのGemini 2.5 Proは2025年3月に公開され、AI性能を評価するLMArenaで首位を獲得するなど高い評価を得ました。コーディング性能や推論能力において強みを示し、コンテキストウインドウ(モデルに一度に入力可能な情報量)が100万トークンと大きく、200万トークンに拡張するとの情報もあります。実運用でこれだけの長文の処理を安定して行えるかは検証が必要ですが、大規模なドキュメント分析やシステム開発でプロジェクト全体のソースコードを理解することが可能になってきているとは言えるでしょう。
Anthropicが提供するClaudeは、Claude 4 OpusやClaude 4.5 Sonnetで構成され、拡張思考モードとして推論モデルが使用可能です。長文コンテキスト理解や対話の一貫性という面で評価されています。なお、以前は会話履歴をAIモデルの学習に用いないという方針を掲げていたClaudeですが、他社同様にオプトアウト(拒否)可能という前提で学習利用されるようなりました。
■推論モデルの台頭
最近特に注目を集めているのが、「推論モデル(reasoning model)」の実用化です。従来のトークン予測型モデル(GPT-4oなど)は、直前の文脈(トークン列)から次のトークンを予測して文章を生成する方式であり、主流でした。一方、推論モデルでは、内部で仮説形成(推論)→その仮説に基づく中間ステップの実行→その結果に応じて最終的な回答を構築する、内部思考の連鎖(Chain of Thought)を処理する設計です。
OpenAIは2025年4月に、o3およびo4-miniという推論モデルを発表しました。o3はコーディングや科学技術分野における推論能力で高評価を得ており、ベンチマークでは従来モデルを上回る結果も報じられています。o4-miniは推論精度をある水準に保ちつつも応答速度やコスト効率を重視したバランス型モデルとして注目されています。
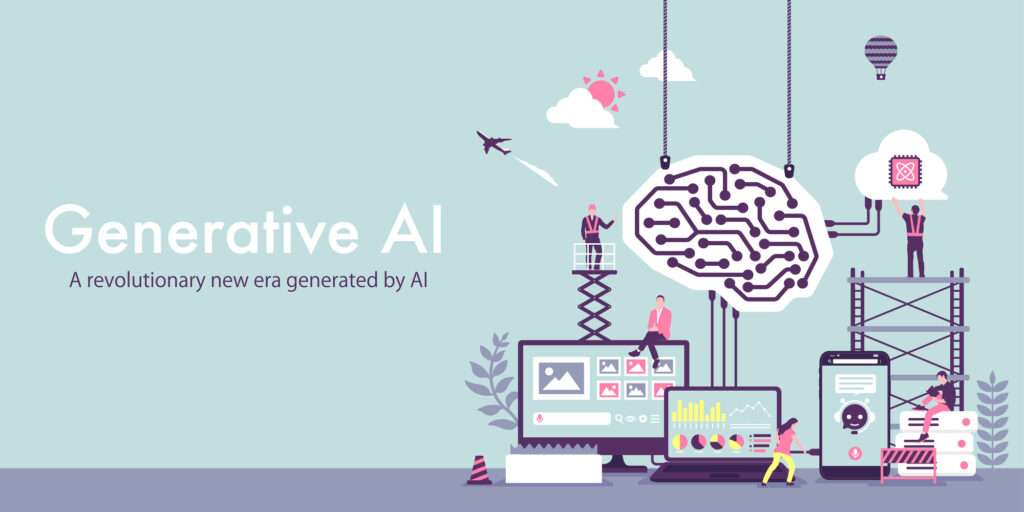
■AIエージェントとDeep Research
ガートナーが例年発表しているハイプサイクルでは、生成AIは2024年版まで「過度な期待」のピーク期に位置づけられていました。2025年版では生成AIは徐々に幻滅期にさしかかり、代わってAIエージェントに対する期待がピークになっています。
2025年は「AIエージェント元年」といえ、リサーチ作業の自動化を担うDeep Researchは、その活用例の一つです。ChatGPTやPerplexity、Grokなどが対応しており、テーマの指示を受けたエージェントが自律的に文献を検索・整理・統合し、専門家水準のレポートを生成します。通常の対話型応答より多少の時間を要するものの、市場調査や競合分析、技術調査などにおいて、人手でのリサーチ時間を大幅に短縮できる可能性があります。
■先進企業の取り組み
企業は実際にどのようにAIに取り組み、成果を生み出しているのでしょうか。
日産自動車は、Azure OpenAI Serviceを基盤とした社内ツール「Nissan AI-Chat」を導入しています。業務時間の短縮と同時に作業品質の向上を目的として、初期段階から本社や開発部門の従業員の約3割が利用しています。
三菱UFJ銀行は、生成AIの導入により月22万時間の労働時間削減を見込んでおり、3年間で500億円を投資する計画を発表しています。事務や営業での活用を進め、生成AIが電話や店頭で顧客対応する「AI営業」も視野に入れています。
トヨタ自動車は、製造現場が自らAIモデルを生成できる「AIプラットフォーム」をGoogle Cloudとのハイブリッドクラウドで開発・運用し、現場主導のDX推進を実現しています。
これらの事例に共通するのは、生成AIを単なる効率化ツールとして扱うのではなく、業務プロセスや組織文化の変革手段として位置づけている点です。但し、規模・領域・目的には各社で違いがあり、その違いこそが実運用での課題と成功要因の分かれ目になるでしょう。
■生成AIは変革のパートナーへ
このように、生成AIは主要モデルの性能向上、推論モデルの普及と実用化、AIエージェントの実装・運用への移行により、業務効率化のための補助的なツールから、業務変革を実現するパートナーへと進化しつつあります。特定非営利活動法人ITコーディネータ協会(ITCA)はデータとITの利活用による変革で持続的な成長を実現する「デジタル経営」を提唱しており、生成AIはその実現を後押しする中核技術といえます。
次回は、生成AIの基礎構造を整理した上で、主要サービスを比較し自社導入時に押さえるべき判断基準を提示していきたいと思います。
※このコラムは全8回を予定しています。

ITコーディネータとして、2016年からAIを業務に組み込む活動を続けている。生成AI利活用クラウドサービス「Gen2Go」を開発・提供するほか、北九州市ロボット・DX推進センターで中小企業のDX支援に携わる。一般社団法人IT経営コンサルティング九州(ITC九州)の理事や、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会生成AI研究会のリーダーも務める。